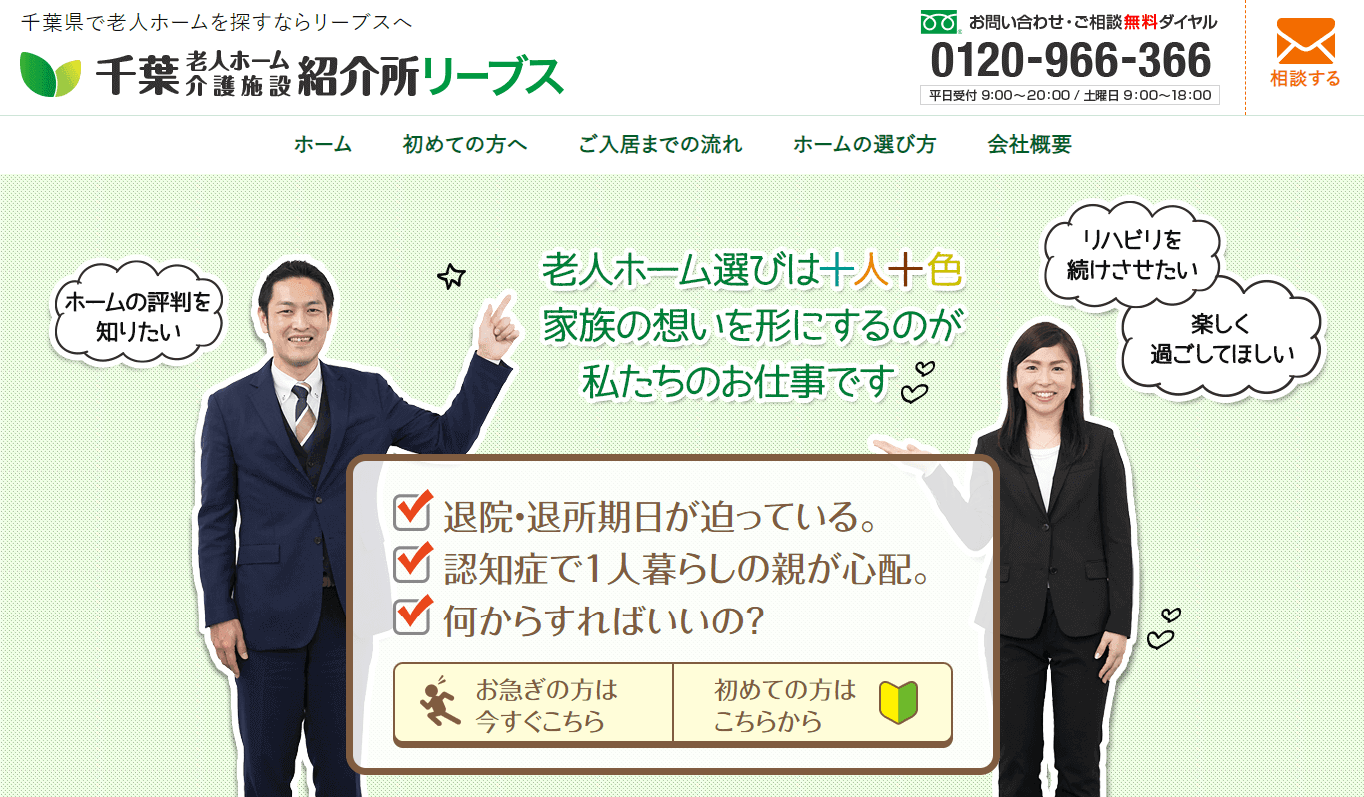特養の3か月ルールとは?

特養とは特別養護老人ホームという公的な福祉施設のことであり、営利目的の民間福祉施設と比べて費用が安く便利です。費用を抑えて手厚い介護サービスが受けられるため、入居希望者が多く、入居まで時間がかかる可能性もあります。せっかく入居できた特養でも退去を迫られる場合があり、そのひとつが3か月ルールです。このルールを知らずに退去勧告をされて困ったことにならないよう、ルールの内容や対処法について紹介します。
3か月ルールについて
特養に入居していて、入院などの事情で3か月以上施設を離れて過ごすとき、施設から退去を勧告される決まりのことを、3か月ルールと言います。施設からしばらく離れることが決まっていても、必ず退去しなくてもよいこともあるため、詳しい内容について知っておきましょう。
3か月ルールがある福祉施設
本来3か月ルールとは、厚生労働省の「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」で定められている第二十二条の内容に沿って、施設が設けている規約です。特別養護老人ホームの運営に関する法律で定めた規約のため、3か月ルールが設けられているのは、特養のみと言えます。
施設規約のもとになった条文では、入所者が入院後おおむね3か月以内に退院した際に、やむを得ない事情がない限り再びスムーズに特養へ入所できるよう対応しなければいけないというものであり、退去を認めるといった内容ではありません。
3か月以内に退院される方は受け入れなければいけないが、入院が3か月を超える場合は再入所の対応をしなくても良い、という解釈で規約に取り入れられています。
3か月ルールで退去勧告されるケース
ルールによって退去を告げられるのは、3か月以上の入院が決まっている場合です。入院期間が3か月を超える場合というのは、ルールの名前通りでわかりやすいケースですが、それ以外の条件でも適用されることがあります。
入院時点では退院の時期が決まっていなくても、入院先の医師から3か月以内に退院できる見込みがないと告げられたときは、規定にのっとり退去しなければいけません。3か月という期間を超える入院という基準で判断がつくため、わかりやすい条件です。
もととなった運営に関する条文にも記載があるように、やむを得ない事情を抱えている場合は特養の再入所ができません。
退院後に日常的な医療ケアが必要である場合は、特養では対応できないと判断され、退去を求められます。設定されている期間内に退院ができたとしても、再入所できない条件が存在している点について注意が必要です。
条件を満たしていても適用されないケース
3か月以上の入院が決まっていても、退去が必須とされない条件があります。入院の原因が入所している特養側にある場合は、長期入院が決まっていても再び戻れるというものです。
具体的には、施設職員の過失による骨折や脱水症状などで長期入院を迫られたときは、3か月以上の入院でも退去を求められない可能性があります。ルールの特性上退去を勧告される可能性も捨てきれないため、トラブルにつながる危険性もあり気をつけなければいけません。
適用されない条件かどうか施設側と話し合ったり、施設とのトラブルに発展しそうな場合は地域の福祉相談窓口やケアマネージャーに相談しましょう。
絶対に守らなければいけない?
入居までに時間がかかり、やっと入れたと思ったら退去を勧告されてしまう規約があることを忘れてはいけません。特養に入居する方は日常的に介護が必要なため、自宅で受け入れるのが難しい場合もあるでしょう。
3か月ルールによって退去しなければいけない状況について、解説します。
規約内容を守らなければいけない
特養の規約で3か月ルールが定められている場合は、守らなければいけません。施設によっては長期入院で退去を告げる期間が3か月ではなく、より長期に設定されていることもあるため、入所時にあらかじめ確認しておきましょう。
法律上の義務ではなく施設の規約であり、適用条件も複雑なことがあるためしっかりと把握しておくことが大切です。
適用に関する考え方のひとつで、累計の入院期間ではなく、再入院時から3か月と数えるとされています。入退院を繰り返したとしても、1回の入院期間が3か月以内であれば再入所できるという考え方ですが、こちらも施設により少しずつ条件が異なる可能性があるため、注意しましょう。
費用面の負担を考慮
3か月以内に退院できそうな状態でも、入院中の費用がかさむ点で、特養を退去した方がよいとされるケースもあります。
特養に入居してから入院した場合、施設にいない間も居住費は支払わなければいけません。再入所まで居住費を払い続けなければいけないため、特養へ支払う費用と入院費を同じ期間負担することになります。
入院中は特養が提供するサービス自体は受けていないため、介護サービスと食事の費用はかかりませんが、スペースを確保している分の居住費用だけ支払うという決まりです。入院中も特養の居住費を払い続けることと、一度退所して退院後に再び入所先を探すことのどちらがよいか、比較して都合に合う方を選べるようにしておきましょう。
施設が受け入れられない条件
定められている期間内の退院ができたとしても、再入所を断られてしまう条件のひとつが、人工呼吸器やカテーテルの管理といった日常的に医療処置が欠かせない場合です。特養には医師が常駐していないことがあり、日々の医療ケアを提供できないため、特養からは退去せざるを得ないということになります。
ある程度の医療処置はできるという施設もあるため、退院後にどのようなケアができるか、施設に確認しましょう。
医療体制が整っていて、日常的な介護サービスも受けられる介護医療院という福祉施設があります。退院後に医療ケアが必要となったときは、特養から介護医療院に移るということも、検討しておくとよいでしょう。
3か月ルールが適用されたときの対処法
特養への入居後に長期の入院が決まり、退去勧告を受けたときにするべき行動について、紹介します。早い段階でしかるべき対処をして、退院後も安心して暮らせる準備を整えておきましょう。
入居中の施設に相談
まず3か月ルールの勧告を受けたときに、特養の担当者と話し合いましょう。状況によっては適用されないケースもあるため、現状をお互いに把握する意味でも丁寧に話し合うことは大切です。
入院当初に3か月以上退院できないと医師から告げられていたものの、回復がよくて早く退院できるということもあり得ます。ルール通りに退去を受け入れたあと退院が早まったとき、再入所したいと相談することで、柔軟に対応してくれる場合もあるため、諦めずに話してみるとよいでしょう。
施設によっては再入所の対応が困難でも、優先的に入所の案内をしてくれるというところもあります。
地域の福祉相談窓口を活用
入居中の施設と話し合いながら、担当のケアマネージャーや地域包括支援センターなどへの相談もしましょう。退去しなくてもよい状況で3か月ルールが用いられているときや施設との話し合いがうまくいかないときに、ケアマネージャーが間に入って対応してくれます。
退所が避けられないときも、退院後に新しく入れる施設を一緒に探してくれるため、早い段階で施設への希望条件をあわせて相談しておくとスムーズです。退院後に新しい施設への入所が間に合わなくても、自宅での生活をサポートしてくれます。
地域の福祉相談窓口を利用することで、希望に合う介護サービスや施設を見つけやすいだけではなく、不安を抱えているときにさまざまな相談ができ、精神的にも安心ができるでしょう。
まとめ
特養の3か月ルールは、法律上の義務ではありませんが、入所時の規約として定められていることです。特別な状況でない限り、施設側から退去を求められた場合、断るのは難しいと考えられます。施設ごとに規約の内容が違う可能性があり、事前に確認しておくことで長期の入院が決まったときに素早い対処ができるでしょう。退去勧告を受けたときも焦らずに施設やケアマネージャーと話し合い、退院後に困らないよう準備しておくことが大切です。
-
 引用元:https://example.com
引用元:https://example.com
現地調査のうえで信頼できる施設を紹介!土日祝日、夜間の訪問対応で忙しい方も安心
リーブス(ひまわりライフサービス株式会社)
【千葉県】おすすめの老人ホーム紹介会社ランキング!
| イメージ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 会社名 | リーブス (ひまわりライフサービス株式会社) | みんなの介護 (株式会社クーリエ) | あいらいふ入居相談室 (株式会社あいらいふ) | ソナエル (株式会社ソナエル) | みんかい (株式会社 ASFON TRUST NETWORK) |
| 特徴 | 自分の家族と接するような気持ちで対応するのがリーブスのモットー | 掲載施設数1位。質・量とも鮮度の高い情報の中から施設を選ぶことができる | 相談から入居まで専門相談員が無料サポート! | 中立公正な立場に立った社会福祉士などの国家資格を持つ相談員に相談できる | 日本初の紹介センター。業界トップの相談経験と実績から培った提案を聞ける |
| 詳細リンク |